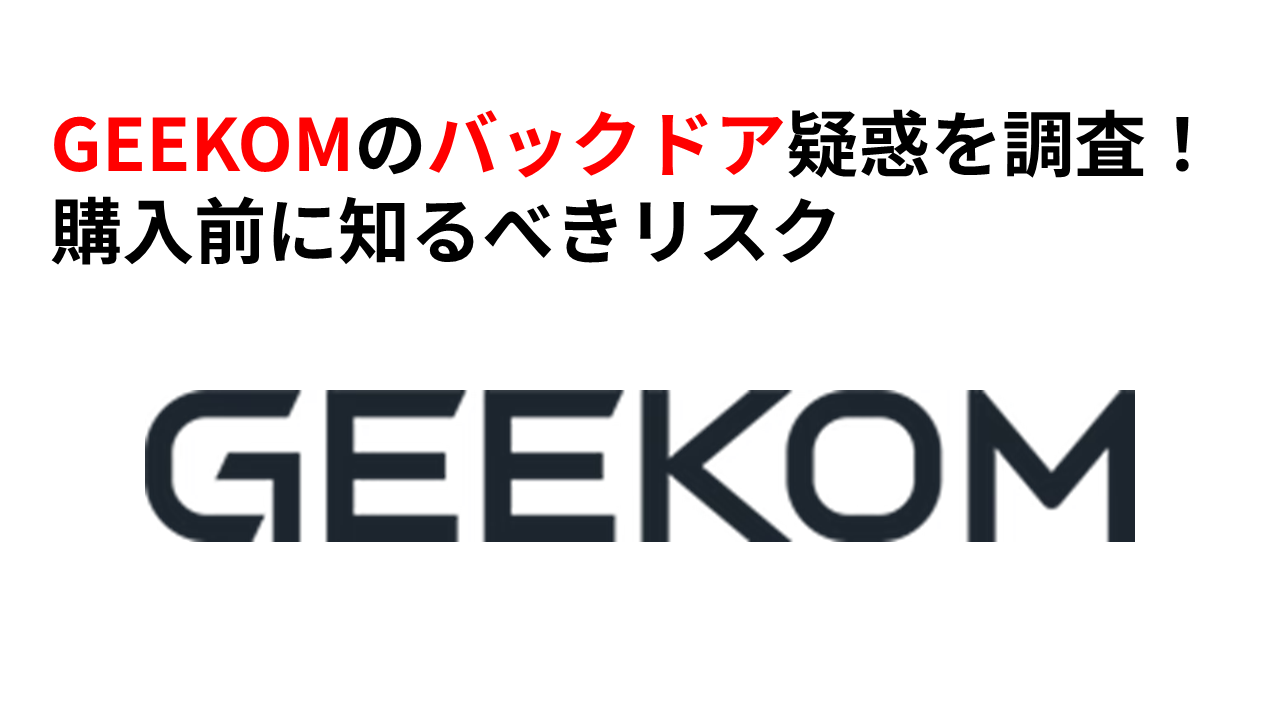「コスパ最強のミニPC」として人気のGEEKOM。
その魅力的な価格と性能に惹かれる一方で、こんな不安や疑問を抱えていませんか?
- GEEKOMのPCには、個人情報を抜き取る「バックドア」が本当に仕掛けられているの?
- 「中国のメーカーだから危ない」と聞くけど、具体的に何が問題なの?
- もし買うとしたら、どんな対策をすれば安全に使えるんだろう…?
圧倒的なコストパフォーマンスに驚きつつも、セキュリティに関する不安な噂は気になります。
先に結論からお伝えします。
GEEKOM製品に、意図的・組織的なバックドアが仕掛けられているという証拠は見つかりませんでした。
しかし、それ以上に深刻な「企業の信頼性」に関わる問題が複数明らかになっており、購入には相応のリスク理解と対策が必須です。
調べた方法(この記事の信頼性について)
この記事では、以下の複数の情報源をもとに、偏りのない客観的な視点でまとめています。
- GEEKOM公式サイト
- Redditのユーザーによる一次報告
- 海外大手テックメディア
- 各種レビューサイト
この記事でわかること
この記事を最後まで読むことで、次のようなことがわかります。
- GEEKOMのバックドア疑惑「トロイの木馬混入事件」
- 技術的な問題よりも根深い「企業の信頼性」に関わる2つの問題点
- 競合製品(Beelink, Minisforum)との具体的なリスク比較
- GEEKOM製品を選ぶ場合に、絶対に欠かせない5つの安全対策
GEEKOMのバックドア疑惑:「トロイの木馬」混入事件
「GEEKOM バックドア」と検索すると、様々な情報が入り乱れています。
その中でも、この疑惑を語る上で絶対に避けて通れない、決定的な事件があります。
新品PCからマルウェアが発見される
すべての始まりは、世界最大級の掲示板サイトRedditへの、あるユーザーの投稿でした。
Amazonで購入した新品の「GEEKOM Mini PC GT13 Pro」を起動したところ、プリインストールされたトロイの木馬が検出された。
検出されたファイルは、通常は表示されない隠しフォルダ C:\ の直下にある llpy.exe という実行ファイル。
これは、ユーザーが何かをダウンロードして感染したのではなく、工場出荷状態の新品PCに、最初からマルウェアが潜んでいたことを意味します。
VirusTotalの分析結果
この報告が単なる勘違いや騒ぎ立てでないことを証明するのが、同時に示された「VirusTotal」の分析レポートです。
VirusTotalは、ファイルを数十種類ものウイルス対策ソフトで一斉にスキャンできるサービスです。
そのレポートでは、有名なセキュリティ企業の多くが、この llpy.exe を悪意のある「トロイの木馬」として判定していました。
これは、もはや「誤検出」では済まされない、客観的な証拠と言えます。
GEEKOM社の対応が最大の問題点
技術的な欠陥は、どんなメーカーにも起こり得ます。本当に問われるべきは、問題が起きた後の「対応」です。
そして、この点においてGEEKOMの対応は大きな問題でした。
投稿者によると、GEEKOMのサポートにこの問題を報告したところ、返ってきたのは「それは誤検出であり、正常な状態です」という驚きの回答だったのです。
参考URL:https://www.reddit.com/r/MiniPCs/comments/1jlis0w/warning_geekom_ai_mini_pc_gt1_mega_came_with_a/
さらにGEEKOMは、その回答の中で自社のFAQページへのリンクを示しましたが、そのページは現在、跡形もなく削除されています。
深刻なセキュリティ報告に対し、調査やリコールをおこなうどころか、問題を「正常」だとするページを作成し、都合が悪くなると削除する。
この一連の対応は、技術的な失敗以上に、企業としての誠実さや信頼性を根底から揺るがすものだと言えるでしょう。
意図的なバックドアか、それとも…?
この事件の原因は断定できません。
- 「意図的なバックドア」
- 「返品された汚染製品が新品として再流通した」
- 「単なる品質管理の失敗」
などが考えられます。
しかし、本質的な問題は、原因が何であれ、「顧客のセキュリティを脅かす深刻な欠陥が見つかった際に、組織として誠実に対応できなかった」という事実にあります。
これが、GEEKOMが抱える最大のリスクなのです。
そもそもGEEKOMってどんな会社?という基本的な情報や、より広い視点での評判については、こちらの記事で詳しく解説しています。
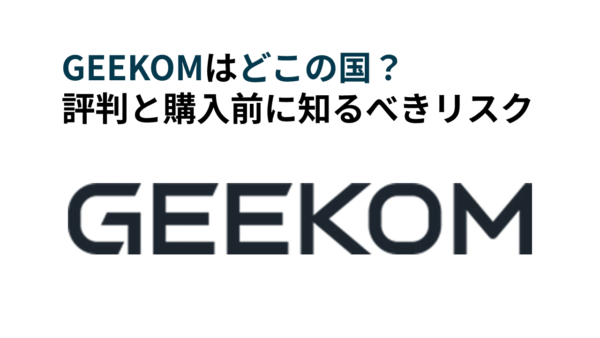
GEEKOMの信頼性を揺るがす2つの問題点
トロイの木馬混入事件は、GEEKOMの信頼性の問題を象徴する出来事ですが、問題はそれだけにとどまりません。
ユーザーコミュニティの報告を調査すると、企業のガバナンス(組織統治)の欠如を示す、さらに2つの根深い問題が浮かび上がってきます。
① 機能不全のサポート体制:3年保証が意味をなさない実態
GEEKOMは公式サイトで「3年間の長期保証」を大々的にアピールしています。
これは競合他社より手厚く、一見すると非常に安心できるように思えます。
しかし、RedditやGEEKOMの公式コミュニティには、この約束とはまったく異なる実態を訴える声があふれています。
- メールを送っても数週間、数ヶ月も返信がない
- サポートの電話番号は誰も出ない
- 保証交換を依頼しても無視される
- 初期不良品を送り返したら、返金も代替品もなく、お金だけ取られてしまった
どんなに立派な保証を掲げていても、それを実行するサポート体制が機能していなければ、絵に描いた餅にすぎません。
万が一、マルウェアやハードウェアの欠陥にあたってしまった場合、ユーザーは救済されずに泣き寝入りを強いられる可能性が高いのです。
機能しないサポートは、それ自体が重大なセキュリティリスクと言えるでしょう。
② 品質管理への不安:初期不良やハードウェア故障の報告
セキュリティ問題に加え、基本的な品質管理を疑わせる報告も数多く存在します。
- DOA(初期不良):製品が届いた時点で電源が入らない。
- 部品の故障:購入後、数ヶ月でBluetoothやWi-Fiモジュールが故障する。
- 接続性の問題:Wi-Fi接続が頻繁に途切れる。
- 熱・騒音の問題:高い負荷がかかるとファンが轟音を立て、本体が高温になりすぎる。
これらの問題は、コスト削減のために冷却設計や部品の品質で妥協している可能性を示唆します。
これもまた、「顧客に信頼性の高い製品を届ける」という、企業としての基本的な責任感が欠けていることの表れかもしれません。
GEEKOMは本当に「やめとけ」?競合製品とのリスク比較
ここまでGEEKOMのネガティブな側面を強調してきましたが、一方でGEEKOM製品を高く評価する声もたくさんあります。
ここで一度、客観的な視点に立ち返ってみましょう。
第三者機関による「潔白」の証明?
テック系レビューサイト「The Gadgeteer」が、ミニPC市場のマルウェア懸念を受け、複数のGEEKOM製品(IT13, AS6, A5など4モデル)を徹底的にスキャンしたところ、すべてのモデルでマルウェアは検出されなかったと報告しています。
これは、GT13 Proのトロイの木馬事件が、GEEKOM製品全体に共通する問題ではなく、限定的な個別の事案である可能性を示す強力な証拠です。
購入者のリスクは、「必ずマルウェアに感染する」というものではなく、「品質管理の甘さからくる“ハズレ”の製品を引いてしまう可能性がある」と考えるのが妥当でしょう。
競合Beelink, Minisforumとの比較表
では、他の中国系ミニPCメーカーと比べて、GEEKOMのリスクはどのレベルにあるのでしょうか。コミュニティでの評判をもとに比較表を作成しました。
| 特徴 | GEEKOM | Beelink | Minisforum |
|---|---|---|---|
| マルウェア事案 | 深刻な報告が1件あり(個別の事案の可能性) | おおむねクリーンな評判 | おおむねクリーンだが、ファームウェアの脆弱性報告あり |
| 主な懸念 | 企業の信頼性、サポート不全 | 比較的少ない | ファームウェア、ハードの信頼性(熱問題など) |
| 公式保証期間 | 3年間(ただし実効性に疑問) | 1~2年間 | 2年間 |
| サポート評判 | 非常に悪い | 比較的良い | 賛否両論 |
| コミュニティ評価 | コスパは最高だが「博打のリスク」が高い | 「より安全な選択肢」 | 性能は最高峰だが技術的リスクも高い |
あなたのリスク許容度は?立ち位置ごとの評価
この比較から、あなたの立ち位置によって評価が分かれます。
価格を最優先し、ある程度のリスクは許容できる
GEEKOM (ただし、後述の安全対策が必須)
安定性と信頼性を重視し、サポートも必要
Beelink (「より安全な選択肢」としてコミュニティの評価が高い)
最高の性能を求める技術者
Minisforum (ファームウェアのリスクなどを自分で管理できる上級者向け)
GEEKOM製品を使いたいあなたへ:必須の安全対策5ステップ
ここまでのリスクを理解した上で、GEEKOMのコストパフォーマンスに魅力を感じる方のために、安全に使うための必須の対策手順を5つのステップで解説します。
前述の通り、GEEKOMの公式サポートは機能していないリスクがあります。
メーカー公式サイトから直接購入するのではなく、返品・返金ポリシーがしっかりしているAmazon(特にAmazonが販売・発送するもの)から購入してください。
これが、万が一の際の唯一にして最大の保険となります。
製品が届いても、すぐに家のWi-Fiに接続してはいけません。まずはインターネットに接続しない「オフライン」の状態でPCを起動し、初期設定をおこなってください。
これにより、万が一マルウェアが潜んでいた場合に、外部との通信を防ぎます。
これが最も重要なステップです。
プリインストールされているWindowsは信用せず、完全に消去してしまいましょう。
Microsoftの公式サイトから最新のWindowsインストールメディアを別のPCで作成し、それを使ってGEEKOMのPCにOSをクリーンインストールします。
インストールの過程で、既存のパーティション(ドライブの仕切り)はすべて削除してください。
クリーンインストールをおこなうと、一部のハードウェアが正しく動作しない場合があります。
その際は、GEEKOMの公式サイトからお使いのモデル用のドライバーをダウンロードして適用します。
ただし、このドライバー自体が不安定さの原因になる可能性もゼロではないことを頭の片隅に置いておきましょう。
OSインストール後、PC起動時に特定のキー(Del, F2など)を押してBIOS/UEFI設定画面に入ります。
「セキュアブート(Secure Boot)」が有効になっていることを確認してください。
これは、OS起動前に悪意のあるプログラムが実行されるのを防ぐ重要な機能です。
また、メーカーサイトに新しいファームウェアの更新がないか定期的に確認しましょう。
あなたの選択は?
ここまでの情報を踏まえ、あなたの選択肢は明確になったはずです。
リスクを理解し、対策を講じる覚悟があるなら、GEEKOMは依然として魅力的な選択肢です。下のボタンから、Amazonで最新モデルと価格をチェックしてみてください。
まとめ
- GEEKOMのPCに、バックドアは本当に仕掛けられているの?
-
意図的・組織的なバックドアが仕掛けられているという証拠はありません。
しかし、新品のPCにトロイの木馬が混入していたという事実が1件報告されており、その後のメーカー対応が不透明であるため、セキュリティリスクは存在します。 - 「中国のメーカーだから危ない」って、具体的に何が問題なの?
-
問題の本質は「中国だから」ということではなく、「企業のガバナンスが欠如していること」です。
具体的には- 深刻なセキュリティ報告に誠実に対応しない姿勢
- 機能していないサポート体制
- 不安定な品質管理
の3点が最大のリスクです。
- もし買うとしたら、どんな対策をすれば安全に使えるの?
-
「OSのクリーンインストール」が必須です。
加えて- Amazon経由での購入
- オフラインでの初期設定
- ドライバーの慎重な導入
- BIOS/UEFIの確認
という5つのステップを踏むことで、リスクを大幅に減らせます。
GEEKOMは、その高いコストパフォーマンスゆえに非常に魅力的なブランドですが、その裏には見過ごせないリスクも存在します。
この記事が、あなたの賢明なPC選びの助けとなれば幸いです。
GEEKOM製品の購入をより広い視点で検討したい方は、こちらの購入ガイドもぜひご覧ください。
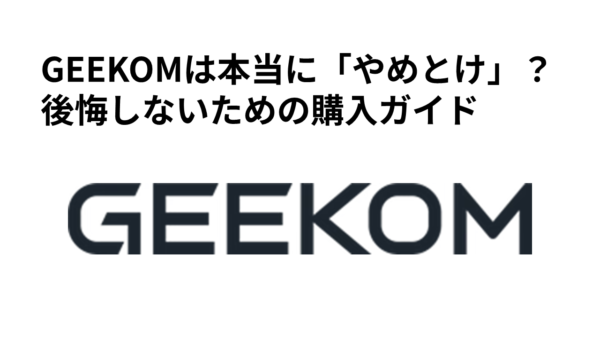
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
主な参考URLリスト
- Reddit – GEEKOM製PCへのトロイの木馬混入報告:https://www.reddit.com/r/MiniPCs/comments/1jlis0w/warning_geekom_ai_mini_pc_gt1_mega_came_with_a/
- The Gadgeteer – 複数ミニPCのマルウェア検査記事:
https://the-gadgeteer.com/2024/02/08/mini-pcs-big-risks-malware-found-on-2-machines-we-recently-reviewed/ - GEEKOM 日本公式サイト:https://geekom.jp/
- Reddit – GEEKOM, Minisforum, Beelinkの比較:https://www.reddit.com/r/MiniPCs/comments/19fjwdk/general_direction_geekom_minisforum_or_beelink/